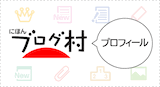こんにちは、Knit BRANCHです。
前回に引き続き、編物検定についてまとめます。
今回は実際に受けてみて思ったことや気になるところを紹介します。細かいところは年度によって変わることもありますから、実際に受検される方は最新情報を確認してください。
良かったところ
理論もあれば実技もある
試験は理論もあれば、実技もあります。
理論の部分は素材のことや色彩のこと、級が上がれば歴史やデザインも含まれます。手引の中のページ数はそれほど多くはないので、さらっと読めます。これで編み物をするときに必要な知識が順に身につきます。
理論の中でも、実技理論というものがあります。3級以上では製図が含まれ、実際の試験では原型から展開して製図します。自分のサイズに合わせて編んだり、新しいデザインを考えたり、製図の知識があるとできるようになります。
そして、実技。試験会場で実際に編みます。その場で初見の編み図を見てその通り編んで提出するというのは、なかなか緊張するものです。時間内に編めるようにと練習することによって、動きに無駄がなくなり、徐々にきれいに編めるようになりました。
まんべんなく勉強できる
毛糸編物検定は1級から5級までありますが、5級からかぎ針編、棒針編、アフガン編の実技が載っています。それぞれの編地には特徴があって、いいところもそれぞれあります。それを早い段階から実感できました。
はじめは広く浅く、級が上がるごとに徐々に深く。編み目の作り方は、かぎ針編みでも棒針、アフガン編みでも5級の手引に載っています。とじ方・はぎ方は4級、引き返し編は3級というようにまとめられています。
一方、レース編物検定は1級から3級までです。ニッティング・レースとクロッシエ・レースは級が上がるごとに高度になります。
それとは別に、各級ごとに出てくる新しいレースもあります。こちらはすべて基礎技術です。色々な種類を経験することによって、自分がきわめたいと思う種類のレース編みが見つかるかもしれません。
例えば、タッチング・レースやマクラメ・レース、バテン・レースなどが載っています。
編み図が読めるようになる
編物検定で使われるのは、JIS記号です。試験対策としては、編み方を実践しながら記号を覚えます。これを覚えると市販されている本に載っている編み図の記号も無理なく読めるようになります。
以下受験の手引からの引用です。
編物にはいくつかの流派があるため本協会役員が最も公共性のあるものを採り上げ、各審査基準にもとづいて記してあります。
確かに細かいところを見れば、少しずつ違う部分はありますが、大きな問題ではないでしょう。よく出てくるものだけでも覚えておくと編み物するときに役に立ちます。
残念なところを少し…
他の検定と違い、結果は合否のみです。7割以上で合格と聞いたことがありますが、実際に何点取れたのか、製図は正しかったのか、編んだものの評価は?と突っ込みどころ満載です。
今は学校などの入試でも、点数開示なるものがあり、点数を確かめることができます。間違った勉強を続けないためにも、詳細な結果が知りたいところです。
編み物を習っている方は、過去問を解いて先生に確認してもらいましょう。それができない場合でも検定前に開催されている各都道府県の講習会がありますから、参加してみてはいかがでしょうか?
最後に
私は受けてきてよかったと思っている編物検定ですが、受検する方は減ってきているようです。残念です。午後の実技を編みあげた後の、やり切った感・充足感をより多くの方に味わってほしいです。
編物検定後のアンケートでは、普段の編み物に役に立っているという意見が多く寄せられています。編み物を始めて少し編めるようになってきたかなという頃が受検を始めるおすすめの時期です。
この記事をご覧になっている方は、ぜひ受検してみてください(^^)/
次回からは、各級ごとのポイントをまとめます。
続きはこちら
編物検定5級に合格するために
最後までご覧いただきありがとうございました。
こちらもおすすめ▼