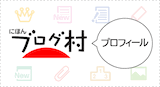こんにちは、Knit BRANCHのtomoです。
前回に引き続き、靴下のかかとの編み方です。
かかとの編み方はこちらから始まっています。お先にどうぞ
今回は編み進む引返し編のやり方と甲側とのつなぎのところがポイントになります。前回と同様、写真を使用して細かいところまで載せていくつもりです。どうぞよろしくお願いします。
靴下のかかとを編む その2
今回は後半部分、編み進む引返し編です。

9段目から14段目にかけて編み進む引返し編をし15段目からは甲側も続けて編んでいきます。⑩段目の矢印がありませんが、右方向です。ここからはまた緑色の糸で編んでいきます。(実際に編むときには、糸を変える必要はありません、すべて続けて編めますよ。)

残す目は、初めが6目、続いて4目・2目と減っていきます。編み進む引返し編では、進むときに段消しをしながら編んでいくようになります。
編み進む引返し編の手順は
- 引返すところまできたら、糸印をつける
- 編地の向きを変え、最初の目はすべらせる
- 続けて編んでいく
- 前の段のすべり目したところまできたら、すべり目のところは普通に編み
- 次の目と糸印を引いてきたループを一緒に編む
- 残す目数のところまで編み進む
- 1に戻ります
続いて、15段目の甲側に進むところです。2つ目のポイントです。どこで2目一度をするか確認して下さいね。

編み図の中で、水色に塗ってある目を編むとき、赤丸印で示した糸印を利用します。左側1回分をはじめに使い、甲側を1段編んでから右側の2回分を使います。

⑥では左上2目一度にします。続いて⑦に進みます。

⑩では右上2目一度をします。そのまま1目編み、⑨と同様に準備して、もう一度右上2目一度をします。
⑨・⑩のところは、右の針に目を移さず、糸印の糸を左の針にかけ、左上2目一度でもかまいません。
これで、すべての段消しが終わりました。かかと側と甲側も、すき間なくつながったと思います。このままぐるぐると輪に編んでいき、つま先に向かいます。
かかと部分はこんな感じになります。


かけ目を使った引返し編と同じような仕組みですが、目のゆるみが少なく引返したところが目立ちません。かけ目した糸がないので、目数も数えやすいやり方です。糸印をつけることが、初めは面倒に感じるかもしれませんが、どこについているかに注目すれば、そのうち印をつけなくても、糸を拾うことができるようになります。私は編み図の赤印のところは注意して編みたいので、今でもつけています。
今回の編み進む引返し編は、スカートの裾をまるくするときに使ったりします。
靴下のかかとの編み方は、本当に多くの種類があって、デザインとして面白いもの、とにかく編みやすいもの、色々ですね。その中の一つの紹介でした。引返しの回数を変えると出来上がる角度も変わります。履き心地のいい角度を見つけてくださいね。