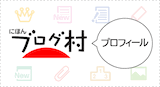「
靴下のかかとの編み方はいろいろありますね。普段は引返し編みを使ったかかとで編んでいますが、ふといろいろ試してみたくなり、実際に編んで比較してみました。
試し編みしたのは、10通りのかかとの編み方。今回は、かかと部分だけを編んでみました。糸はすべて同じものを使用しています。基本は1周48目、そのうち半分の24目を使用してかかとを編んでいます。
80㎝の輪針を使い、マジックループの方法で編みました。
使用した針▼
個別の写真はすべて、(1枚め)左側が表、(2枚め)右側が裏です。
- ①いつもの靴下:引返し編み使用
- ②いつもの靴下を1目ごとの引返し編みにアレンジ
- ③ラップ&ターンで引返し編み
- ④ドイツ式引き返し編み
- ⑤三角に減らしながら編んで拾う形
- ⑥後付けするかかと
- ⑦Opal糸オリジナルの編み図:ボックス型靴下のかかと
- ⑧ユキロザさんの靴下のかかと:三角マチが入る形
- ⑨「マルティナさんの富士山かかと」より
- ⑩「まっすぐあむだけ びっくり!くつ下」より
- 番外かかとなし:「スパイラルソックス」より
- 編んでみて・・
- おすすめの本
- おすすめの糸や道具
①いつもの靴下:引返し編み使用


▲かけ目を使わず糸印を使って引返し編みをする方法です。かけ目を使わないことにより、すき間は少なめ。2目おきに引返しをするので、編み目もゆるみにくいです。
かかとだけ色を変えたり、もう1本糸を引きそろえて補強したりしてもおもしろいですね。はき口から編んでも、つま先から編んでも使える方法です。
欠点は、引返し回数が少なくなってしまうこと。厚みのある足の場合は、足裏の部分に引返し編みを追加をしたりして対応しています。
本体をゴム編みで編むときなど、目数が多い靴下の場合は、その分引返せる回数が増えるので、問題ありません。
②いつもの靴下を1目ごとの引返し編みにアレンジ


▲①の引返し編みを使用したものと仕組みは同じです。
①では2目ごと残しながら引返し編みをしていますが、ここでは甲側に近い方を1目ごとの引返し編みに変更して編んでいます。その分、引返す回数が増えるので、かかとには、より大きな角度をつけることができます。
写真は、片側につき2目ごとが2回、1目ごとが4回で、合計6回引返しました。どうしても1目ごとの引返し編みは、あいだが空いていることが少し気になりますが、履き心地には影響ありません。角度が深くなった分、かかとを包まれている感じ。
2目ごとをやめ、1目ごと6回でも見た目はほとんど変わりませんでした。混乱する場合は1目ごと6回の方が編みやすいです。
③ラップ&ターンで引返し編み


▲ラップ&ターンの方法で糸を巻き付けながら編んでいます。
今回は片側につき1目ごと6回ラップ&ターンしました。 ラップ&ターンのいいところは、余分の糸が針にかからないこと。かけ目の糸があると、目数の数え間違いにつながることもあります。
ラップ&ターンは、引返す1目手前で操作を始めます。段消しはラップした糸とラップされている編み目とを一緒に編みます。
ラップした糸を見落とさないように注意が必要。でも、小さめのラップじゃないと目立ってしまう。慣れれば問題なしです。
こちらにもまとめています▼
④ドイツ式引き返し編み


▲ドイツ式の引返し編みを使用して編んでいます。ジャーマン・ショート・ロウ。今回は1目ごと8回引返ししています。
ドイツ式のいいところは、引返す操作も段消しも、表・裏同じ手順でできるところ。
表でも裏でも引返すところまできたら編地を裏返し、糸を手前に持ってきてから端の目をすべります。
これから編む糸を針の上から向こう側に回すように引き、一段下の目が針にかかるようにします(糸が2本かかったようになります)
段消しをするときは、そのかかっている2本を一緒に左上2目一度で編めばいいのです。
英文パターンのように、操作方法のみを見ながら順に編むときには問題ありませんが、日本の一般的な編み図を見ながら編むときには、少し混乱するかもしれません。
段消しの時、針にかかっているかけ目と次の目を一緒に編むのではなく、2本かかっているものを一緒に編むというところが混乱の原因かなと思いますが、慣れればとっても楽な方法です。
⑤三角に減らしながら編んで拾う形

拾い方はこんな風に▼



▲三角に減らしていき、端の目を拾いながら増やしていくパターン。引返し編みは使わないけれど、できあがりの形は似ています。
あらかじめ編んでいく形が想像しやすいパターンなので、初心者の方にもおすすめ。減らしていくときは、はしの目を2目一度して、増やすときは編み地から拾って新しい目を作りながらかかとを編んでいきます。
この編み方の一番いいところは、間違えたときに戻りやすいこと。初心者の方が、とにかく靴下を編みたいという時には、このかかとの編み方がおすすめです。
かかとだけ色を変えることもできますし、向きは変わりますが、はき口から編んでもつま先から編んでも使える方法です。
欠点は見た目でしょうか?裏側はあまりゴロゴロしませんが、表は少しボコボコするので、ピッタリの靴を履いたりすると、押されて痛いかも。
⑥後付けするかかと


▲かかと部分に別糸を入れておき、後からほどいて目を拾い、かかとを編みます。かかとに穴が開いてしまったら、何度でも編み直すことができる方法です。
かかとにする部分に、ポケットを編むときのように別糸を入れておきます。最後にそこをほどきながら目を拾い、靴下のつま先を編むように4か所で減らしながら編んでいくと、かかとになります。
かかとだけ別の色で編むと、ポイントになってかわいいし、編み直すときも目を拾いやすいと思います。別糸から目を拾うところがきもですから、そこはていねいに行いましょう。
今回はまず目を拾い、1段はそのまま表編みで編んで、次の段で目数調整をしました。いきなり編み始めるより、甲とのつなぎ目がきれいに仕上がると思います。
⑦Opal糸オリジナルの編み図:ボックス型靴下のかかと


▲この編み図は、「Opal毛糸の製造販売元のTUTTO社がウェブページで公開している、ドイツ流の靴下の編み方を同社の許諾を得て日本語に翻訳したもの」だそうです。
編み図はこちらでご覧いただけます▼
Opalオリジナル ドイツ靴下の編み方 - Opal/Schoppel毛糸とaddi編み針の専門店【けいとや】
はき口から編んでいくタイプのボックス型かかとです。
早見表を見るとサイズが豊富に展開されているので、Opalの糸で編むならそれを参考にすぐに編み始められます。
まずかかとの長方形部分を編み、かかと底を編んで目を拾って三角まちを編んでいきます。目を拾う部分があるので、1本線が入ります。裏側の拾ったところがゴロゴロが気になる方は、次のユキロザさんのかかとの方が、向いていると思います。
そのままの説明で編むと、どうやら右上2目一度の代わりにねじり目を利用しているよう。左右で見た目が変わるので、そこは適宜アレンジしてもいいのかなと思いました。かかとは長方形に編むだけなので、ぜひ模様を入れて楽しみたいですね。。
ボックス型かかとは、本体の目数が同じ場合、引返し編みを使用するよりボリュームのあるかかとが編めるので、甲が高い方に向いていると思います。
⑧ユキロザさんの靴下のかかと:三角マチが入る形


▲けいとやさんの販売サイトで見つけました。けいとやさんのサンプルを編むためにも使われているそうです。
ユキロザさんのブログはこちら▼
ユキロザの「つま先から編む靴下の編み方」 – Paws@Work
こちらはつま先から編んでいくタイプのボックス型かかとです。
表示通りの54目で編みました。(かかとの模様は入れ忘れました、すみません)
ボックス型かかとですが、目をまとめて拾うところはないので、裏もゴロゴロしませんよ。ユキロザさんのページでは、自分のサイズに合わせて編めるような提案がされていますので、ぜひご覧になって編んでみて下さい。
次回この方法でかかとを編むとしたら、スニーカーソックスみたいな形に挑戦したいです。かかとはしっかり包まれそうだし、最後の何段かの色を変えて靴からちらっと見えるのもいいですよね。
ここからはデザイナーさんオリジナルの編み方です
⑨「マルティナさんの富士山かかと」より
Opalの糸で編む靴下で使用されている、富士山かかとの編み方です。こちらを参考に編みました▼


▲まず、はしを減らし目しながら三角に編みます。そして、拾ったところをそのまま編み目として利用しながら目を増やして、かかとを編む方法です。
少し詰まった仕上がりになりました。伸びのいいソックヤーン向けの編み方です。
今回はすべてマジック・ループの方法で輪針を使用し編みましたが、この方法は輪針だけでは、編みにくいところがありました。動画にあるように、短針で編む方法です。
⑩「まっすぐあむだけ びっくり!くつ下」より
今回は他と同様に編むため、少しアレンジして輪で編んでいます。最後にとじる必要があります。


▲かかとを作るために、ガータ編みの伸縮性を利用しています。メリヤス編みとガータ編みのゲージや伸縮性の違いを利用して編むかかとです。
何段分ガータ編みを入れるかは、様子を見ながら調整できるのでとても便利なテクニックです。わきの部分は最後にとじるので、裏から見ると左右に1本ずつ線が入ります。
この形のように編むと、ひじのサポーターみたいですね。
番外かかとなし:「スパイラルソックス」より
ゴム編みをらせん状にずらしながら編んでいく方法です。かかとをあえて作らなくても靴下になる、スパイラルソックス。ずらし方はいろいろだと思いますが、ケストラーさんの本を参考に編んでみようかなと思っています。
編んでみて・・
今回まとめて試してみたかかとの編み方は、大きく分けると引返し編みを使った編み方、ボックス型に編んでいく編み方、それ以外の便利な方法という3種類に分けられました。
色々編んでみましたが、現在はいつもの2目ごとの引返し編みかドイツ式の引返し編みに落ち着いています。
今回はとにかくかかとだけ編んで、思いつくまま感想をまとめました。個人の感想ですから、参考程度に。お気に入りのかかとが見つかるといいですね。
今回は靴下のかかとの編み方の比較でした。
おすすめの本
おすすめの糸や道具
今回も使用した輪針。4plyのソックヤーンなら1号、太めなら3号くらいで編んでいます▼
短針でももちろん編めます。号数は糸の太さに合わせてね ▼
糸はソックヤーンがおすすめ!ナイロンが入っているから丈夫です▼
マルティナさんで有名なKFSさんにはオリジナルの素敵なカラーもたくさん▼
この糸にしかないグラデーション。編んだらとっておきの1足になります▼
段数を数えるときに便利なのはこちら▼
最後の糸処理もていねいに▼
私が最近編んだ靴下はこちらです。

染色用ソックヤーンを染めて編んでみました。染めもまた楽しいですd(^_^o)